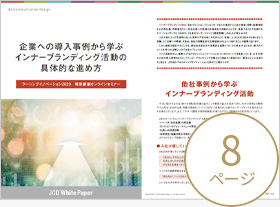近年、日本の労働環境は大きな変革期を迎えています。少子高齢化、デジタル化、そしてコロナ禍を経て、働き方の変化など、さまざまな要因が重なり、従来の労働慣行では対応しきれない状況が生まれています。このような背景のもと、政府は働き方改革以降、一連の法改正を進めています。

● 法改正はなぜ行うのか?
社労士として、「法改正は義務、罰則があるから、やらざるを得ない」という声をよく耳にします。しかし、法改正に対応する本質を理解することで、その考え方は変わります。
皆様もよくご存じの「働き方改革」を例にひも解いてみましょう。
1)「働き方改革」が目指すもの
働き方改革に対して、「従業員が楽をするだけの改革という不満」との声も聞かれますが…、厚生労働省が目指す働き方改革の本質は以下の通りです。
• 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少への対応
• 育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化への対応
• イノベーションによる生産性向上
• 就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境の創出
働き方改革の本質は、人材不足時代に備えて、組織と個人とのコミュニケーションを円滑にし、多様な人材と働き方を推進し、企業の生産性を高めることにあります。
2) 法改正の背景と必要性
①多様な働き方への対応
②少子高齢化への対策
③労働生産性の向上
このように、法改正は単なる規制強化ではなく、変化する社会情勢に対応し、企業と労働者双方にとってより良い労働環境を構築するための前向きな取り組みです。
次のパートでは、これらの背景を踏まえた具体的な法改正のメリットについて解説いたします。
3) 企業が法改正に対応する7つのメリット
①優秀な人材の確保と定着
多様な働き方への対応や、育児・介護との両立支援強化により、優秀な人材を惹きつけ、長期的に定着
させることが可能です。
②従業員エンゲージメントの向上
公平な待遇や働きやすい環境整備は、従業員の満足度とモチベーション向上に寄与し、生産性向上や創
造性の発揮を促します。
③企業イメージの向上
法改正への積極的な対応と魅力的な職場環境の整備は、企業のブランドイメージ向上につながり、顧客
や取引先からの信頼獲得やビジネスチャンスの拡大に貢献します。
④リスク管理の強化
ハラスメント防止対策やフリーランスとの適切な取引関係構築など、法令遵守の徹底は、訴訟リスクや
風評リスクの低減につながり、企業の持続可能性を高めます。
⑤イノベーションの促進
多様な人材が活躍できる環境整備は、異なる視点や経験を持つ従業員間の相互作用を促し、イノベーシ
ョンを促進します。これは、新製品開発や業務プロセス改善など、企業の競争力向上につながります。
⑥労働生産性の向上
働き方改革を通じた長時間労働の是正や業務効率化は、労働生産性の向上に直結し、企業の収益性改善
に寄与します。
⑦社会的責任の遂行
法改正への適切な対応は、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにもなります。これは、持続可能な
社会の実現に貢献するとともに、投資家や消費者からの評価向上にもつながります。
4) 法改正はチャンスと捉える
法改正は、企業にとって対応すべき課題であると同時に、大きな機会でもあります。法改正の情報は、最新のビジネストレンドを知る重要な指標です。先行している企業は、法改正前から対策を進めて差別化を図っています。これらの対応には、単に就業規則の修正だけでは不十分です。人事制度の見直しや業務プロセスの改善など、総合的な変革が必要となります。経営層のリーダーシップのもと、法改正の意義を会社のビジョンやパーパス(志)に落とし込み、変更する目的を従業員と共有することが大切です。また、デジタル技術を活用した人事労務管理システムの導入も、これらの変革を効率的に進める上で有効です。
5) 直近の主な法改正
①雇用保険表の改正(2025年4月)
失業保険(基本手当):自己都合離職者の給付制限の緩和 2か月→1か月
②高年齢雇用継続給付の見直し
支給率が15%上限から10%上限に変更
③育児・介護休業法の改正(2025年4月、10月)※就業規則の改定必要
子の看護休暇の見直し、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取‧配慮が義務化 等
④育児時短就業給付の創設(2025年4月)
⑤障害者雇用率制度」“除外率”が引き下げ
⑥職場における熱中症対策が義務化(2025年6月)
※罰則あり:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
● 法改正/制度改定の効果を高めるために
効果を高めるためには、以下の5つの評価項目に対して現状を確認し、個別の課題に対して施策を検討・実施する必要があります。
1.ビジョン
2.風土
3.労働環境
4.各種制度
5.人材活用
現状把握には、リアルコミュニケーションによるヒアリングだけでなく、ITを活用したサーベイ(アンケート)の実施と分析が有効です。
● 最後に
法改正への対応を、単なるコンプライアンスの問題としてではなく、企業の持続的成長と競争力強化のチャンスとして捉え、積極的に取り組むことが重要です。これにより、変革の時代を乗り切り、未来への道を切り開くことができます。法改正は「事業継続の要」なのです。
今後、法改正の新しい話題、活用のコツなどについて、随時、発信をしてまいります。
法改正、制度改定、組織診断調査等でお悩みのことがあれば、ぜひご相談ください。

HRコンサルティング事業局
プロデューサー (社会保険労務士) 田邊良学
 (株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。
(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。
現在はJTBコミュニケーションデザインにて、組織開発ソリューション「WILL CANVAS」を担当。新規事業開発の経験と社労士としての専門知識を融合させて、事業戦略と人事戦略の両面から企業の成長を支援している。
【資格】社会保険労務士、両立支援コーディネーター、運行管理者資格者(旅客)、海外安全・危機管理責任者、防災士、など。
企業への導入事例から学ぶ
インナーブランディング活動の具体的な進め方
JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。
- 人と組織
- 2025/08/26