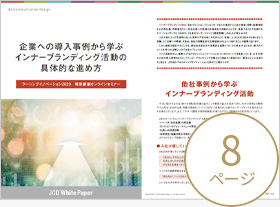2025年度の最低賃金改正により、ついに全国すべての都道府県で最低賃金は1,000円を突破し、全国加重平均は過去最高を更新しました。今後は「時給1,500円」に近づく流れが現実味を帯びています。この改正は、単なる人件費アップにとどまらず、経営の方向性を問い直すシグナルでもあります。
今回は経営者目線で、最新動向と対応戦略を整理します。

Ⅰ.最低賃金改正の最新動向
(1)全国平均:過去最高水準
全都道府県で1,000円を超え、東京・神奈川だけでなく、地方圏も引き上げ幅が大きくなっています。

出典: 沖縄タイムス2025年9月5日
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1663724
(2)政策的目標は最低賃金「1,500円」
政府の中長期方針として、最低賃金を2020年代に全国加重平均で1,500円に引き上げる計画が進んでいます。労働分配率を高め、非正規・正規の格差を縮小する流れが続いています。 時給1,500円になると、1日8時間、20日勤務をした場合、24万円/月となりますので、非正規、正規の賃金格差が、さらになくなることになります。
(3)最低賃金改正の社会保険適用拡大への影響
通称「106万円の壁」は、2016年に501人以上の企業で義務化が始まりました。段階を経て下限が下がり、2024年10月からは従業員51人以上の企業で、週20時間以上の短時間労働者の社会保険加入が義務化され、「年収の壁」を理由とした就労調整の動機が弱まっています。

出典: 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html
(4)なぜ106万円の壁が撤廃されるのか?
厚生労働省は、社会保険制度をより公平で現代の労働市場に合ったものにするため、2026年10月をめどに106万円の壁の撤廃を決定しました。
➊年収要件撤廃の背景
・労働力不足対策 106万円の壁を意識している労働者は約65万人と推計されており、壁の撤廃により働き控えを解消し、労働力確保を期待しています。
・最低賃金上昇による必然的な年収増加 週20時間勤務の場合、時給が上がれば自動的に年収106万円を超えることになります。
<最低賃金と106万円の壁のシミュレーション>
・週20時間 × 52週(1年) ÷ 12ヶ月 = 月約87時間
・106万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 87時間 = 時給約1,016円

出典: 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
【参考】 企業規模要件は10年後の2035年に完全に撤廃されるため、50名以下の企業も撤廃時期を見据えた人件費対策が必要となります。

出典: 厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001505993.pdf
➋経営者への実務的な影響
2025年度の最低賃金は最低額1,023円となり、全国で前述の1,016円を超えることになりました。週20時間以上の勤務では106万円の壁を避けられない状況となっています。
・社会保険料負担の増加:106万円の壁を超えると、会社・従業員ともに賃金の約15%を負担(労使合計:約30%)となります。
・従業員の手取り減少への懸念:社会保険料負担により、労働時間を減らす調整や社会保険がかからない職場への転職者が一時的に増える可能性があります。
・就労調整の減少:壁を超えることが確実な従業員は、逆に積極的に労働時間を増やす動機となり、生産性向上につながります。
経営者としては、この変化を「コスト増」として捉えるのではなく、「優秀な人材の戦力化機会」として活用することが重要です。
Ⅱ.経営者にとってのリスクとチャンス
最低賃金の上昇をリスクとチャンスの視点でまとめてみます。
◆リスク
•人件費の急激な上昇 → 利益圧迫、特に人件費比率の高い業種への影響
•非正規・正規の賃金差縮小 → 正規社員のモチベーション低下リスク
•人材流動化の加速 → 賃金以外の魅力が乏しい企業からの人材流出
◆チャンス
•賃金体系の再設計機会: 公平感のある処遇制度の構築
•非正規の戦力化: 「人件費=コスト」から「人材=資本」への転換
•生産性向上の契機: DXや業務効率化投資の推進による競争力強化
Ⅲ.経営者が取るべき具体的な対策
(1)人件費対策
◆ステップ1:人件費シミュレーションの実施
最低賃金改正後の総人件費を正確に算出することが第一歩です。時給だけでなく、賞与・各種手当・社会保険料まで含めたトータルコストの把握が重要です。
◆ステップ2:処遇体系の見直し
正規と非正規の職務評価の明確化を図り、職務給やスキル基準を設定して昇給の根拠を明確にします。これにより不満や「逆転現象」(非正規>正規)を防ぐことができます。
【実務例】
同一労働同一賃金対策も踏まえて、正規・非正規社員に「資格取得奨励金」を設けて、成長意欲を高めつつ、非正社員のキャリア形成として正社員転換制度を推奨します(正社員転換には、キャリアアップ助成金の活用を検討)。キャリア形成・役割拡大を重視した昇給設計を行います。
◆ステップ3:従業員のモチベーション対策
最低賃金上昇で非正規の賃金が急速に上がる一方、正規との格差が縮まることで、「責任は重いのに給与差が少ない」と正規社員の不満が高まりやすくなります。これを放置すると、優秀な正社員の流出につながりかねません。
【実務例】
賃金アップ後のモチベーション、3か月後等の変化を調査し、継続的なモチベーション対策(調査結果のフィードバック、個別面談)を実施します。
◆ステップ4:生産性向上への投資
・業務プロセスの標準化・DX導入による効率化
・マニュアル整備による属人化の排除
・AI・RPA活用による定型業務の自動化
【実務例】
バックオフィス業務のクラウド化により事務処理時間を削減し、その分の人件費を現場の処遇改善に回します。
(2)対策の例
給与が他社との差が縮まるため、これからは「成長できる会社」「働きやすい会社」との認識を得ることで、採用力・定着率の向上につながります。
・企業理念の共有
パーパス(存在意義)を明確化し、従業員の誇りと帰属意識を醸成
・役割給の明確化
責任範囲やマネジメント業務を正当に評価
キャリアパスの明示:「給与+将来の役職・成長機会」をセットで提示
・非金銭的報酬の充実
裁量権の拡大、在宅勤務制度、休暇制度、資格取得支援
表彰制度・承認の仕組み:成果や挑戦を組織として承認する制度導入
・賃金以外での差別化戦略
柔軟な働き方の提供: 在宅勤務制度、時差出勤、短時間正社員制度の導入
福利厚生の強化: 資格取得支援、キャリア研修、健康経営施策、社内コミュニティ形成
・助成金の活用:業務改善助成金(中小企業対象)
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行
った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。本助成金を活用することで、生
産性向上のための設備投資費用を軽減できます。効果的な申請のタイミングは、2025年の最低賃金が施
行される前となります。助成金を活用することで、事業場内最低賃金を30円引き上げるだけで、1人あた
り助成額の上限が30(60)万円、90円引き上げで120(170)万円となります。
※()内は30人未満規模の場合の助成額上限
Ⅳ. 経営視点の転換:「コスト削減」から「人的資本投資」へ
最低賃金の引き上げは「国が示すメッセージ」でもあります。それは、労働力を安価に活用する時代から、投資して育成する時代への転換です。経営者として問われるのは以下の2点に集約されます。
・単なる対応ではなく、賃金改定を「企業の競争優位性構築」にどう結びつけるか
・従業員のエンゲージメントと生産性をどう同時に高めるか
Ⅴ. まとめ
•2025年度、最低賃金は全国で1,000円を突破
•中長期的には「時給1,500円時代」を見据えた経営+人事戦略の検討が必要
•非正規との格差縮小により、正規社員のモチベーション管理が鍵となる
•経営者には「賃金以外の差別化」と「人的資本投資」の視点が必要
最低賃金改正は、負担ではなく経営を強化するチャンスです。正規・非正規双方のモチベーションを高め、人的資本経営の視点で取り組む企業こそが、次の時代の競争を勝ち抜き、事業継続につながります。

HRコンサルティング事業局
プロデューサー(開業社会保険労務士) 田邊 良学
 (株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。
(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。
現在はJTBコミュニケーションデザインにて、組織開発ソリューション「WILL CANVAS」を担当。新規事業開発の経験と社労士としての専門知識を融合させて、事業戦略と人事戦略の両面から企業の成長を支援している。
【資格】社会保険労務士(開業)、両立支援コーディネーター、運行管理者資格者(旅客)、海外安全・危機管理責任者、防災士、など。
企業への導入事例から学ぶ
インナーブランディング活動の具体的な進め方
JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。
- 人と組織
- 2025/09/22